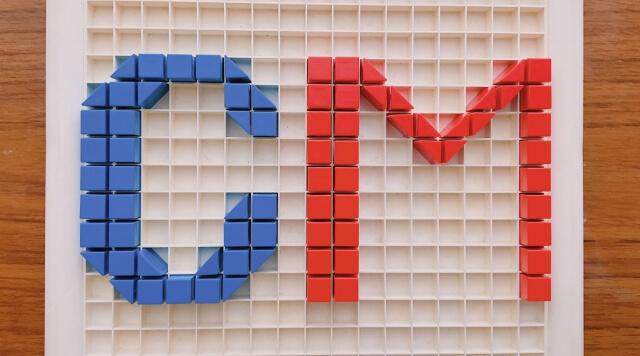
わずか数十秒で心をつかむ、日本のCM文化。その魅力と進化を紐解きます。
9月7日は「CMソングの日」です。1951年のこの日、日本で初めてCMソングがラジオから流れたことにちなんで制定。記念すべき第一号は、小西六写真工業(後のコニカ)の「僕はアマチュア・カメラマン」という曲で、広告と音楽の結びつきが本格的に始まった瞬間でした。
このCMソングの日をきっかけに、あらためて日本のCM文化を振り返ってみると、そこには独自の進化と美意識が見えてきます。まず注目すべきは、海外との違いです。欧米では“イメージを損なう”との理由で、映画俳優がCM出演を敬遠する傾向がありますが、日本では国民的スターから世界的俳優まで自然に登場します。海外から訪れた人々が、日本のテレビでアメリカの有名俳優が缶コーヒーや家電製品を紹介している様子に驚くのも無理はありません。

また、日本のCMは“短編映画”のような感動を与えることで知られています。わずか15秒から30秒ほどの中に、人生のドラマや家族の情愛を描き出し、その背後に流れる情感豊かな音楽が視聴者の心を揺さぶります。こうした演出は単なる宣伝を超えた映像芸術としても評価されることがあり、日本独自のCM美学ともいえるでしょう。
その一方で、日本ではCMソングがヒット曲として大きな成功を収めることは、もはや必然の事実。とくに80年代から90年代にかけて、CMソングが際立って華やかな時代でした。JR東海のキャンペーンで使用された松任谷由実「シンデレラ・エクスプレス」や、山下達郎「クリスマス・イブ」は、その映像と楽曲が一体となった世界観が話題を呼び、広告業界においても大きなインパクトを残しました。

同じくJALの夏の沖縄キャンペーンでは、米米CLUB「浪漫飛行」や上々颱風「愛より青い海」もCMをきっかけに大ヒット。とくに化粧品会社の季節キャンペーンソングは注目されました。桑名正博「セクシャルバイオレットNo.1」やラッツ&スター「め組のひと」、堀内孝雄「君のひとみは10000ボルト」、渡辺真知子「唇よ、熱く君を語れ」など、今なお愛される楽曲の多くが、CMをきっかけに世に広まりました。

こうした季節ごとの広告と異なる菊正宗のCMソングの特徴はロングランです。1975年から約30年間にわたり放映された菊正宗のCMでは、紫の風呂敷をシンボリックに“甘口が多いとお嘆きの貴兄に…”というナレーションとともに、西田佐知子の「初めての街で」が流れました。その後、映像が変わっても同じ曲が流れることで、伝統と一貫性を印象づける効果は高く、ブランドの歴史そのものを表現する役割を果たしたといえるでしょう。

CMの映像と曲調、そして歌詞のフレーズがぴたりと一致すると、その相乗効果は絶大です。まさに“ヒット曲はCMから生まれる”といわれた時代でした。何より、それまで気にも留めていなかったアーティストの楽曲がふと耳に残り、気づけば口ずさんでいた…そんな新しい音楽との出会いの場でもあったのです。CMは、商品紹介を超えて記憶や人生のワンシーンに結びつく存在です。9月7日のCMソングの日には、そんな“音と記憶の結びつき”に、少し耳を澄ませてみてはいかがでしょうか。
「菊正宗 超特撰 嘉宝蔵 雅 1.8L」
菊正宗のCMとして登場していたのが、純米酒「雅」!
現代風にリニューアルして、現在も日本酒ファンに大変人気の商品です。
兵庫県三木市吉川・口吉川 「嘉納会」特A地区産 山田錦100%使用。
酒蔵を継承することは、先人達の想いを継承すること。山田錦のポテンシャルを高度に引き出す、嘉宝蔵・生酛の寒造り。最高の素材と変わらぬ造りが「百年変わらぬ味わい」を未来へと引き継ぎます。
奥深いうまみと余韻が綺麗に引き締まる、官能的なフルボディ。これが、菊正宗が誇るうまい辛口の王道。究極の「灘の生一本」です。

菊正宗ネットショップはこちらから
▼https://www.kikumasamune.shop/


















