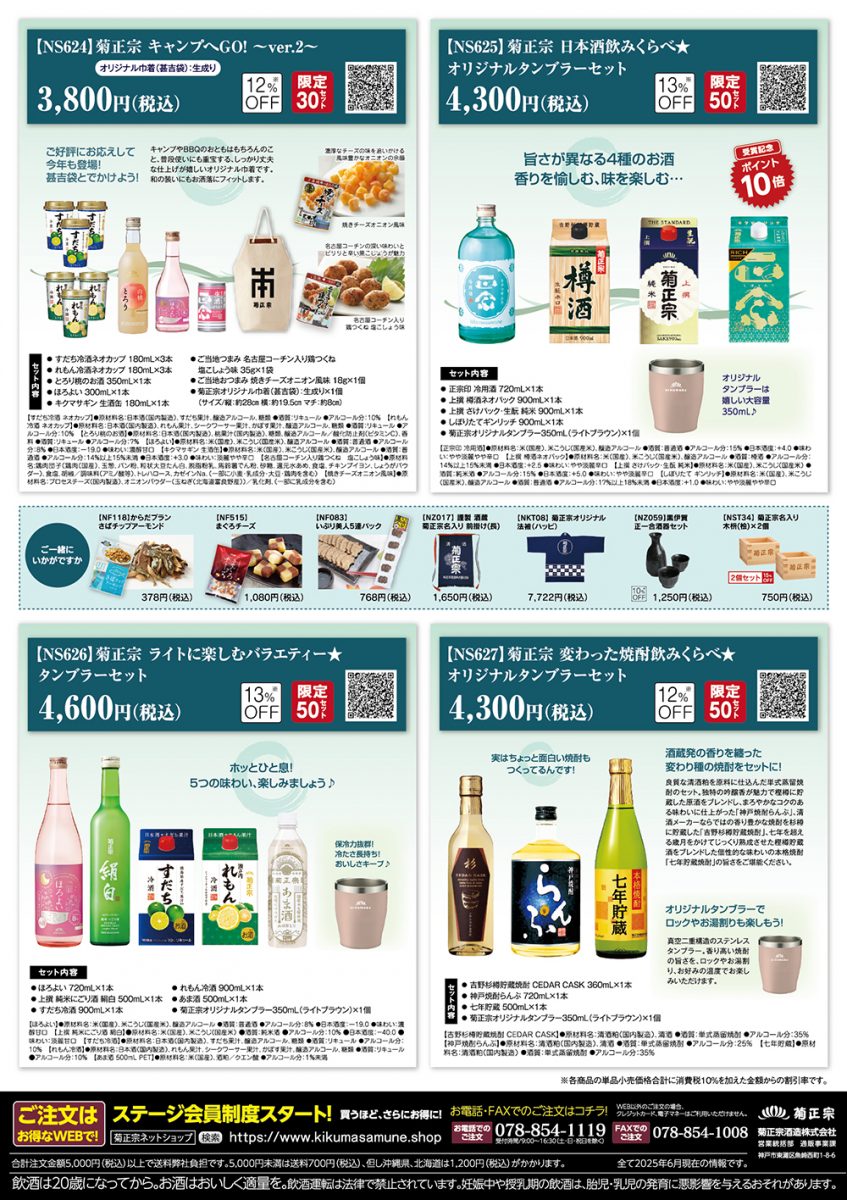今年の土用は、養殖“メスウナギ”を。トレンドの進化系ウナギで夏を乗り切る。
短い梅雨を追い越すように、いきなり40度近い猛暑が続いています。早くも熱中症が心配されるこの時期、まもなく土用の丑の日です。暑気払いのスタミナ源としてのウナギは、すっかり夏の風物詩として定着。照りつける太陽に体力を奪われる盛夏、ウナギの脂と栄養価は、滋養をつけるための理にかなった食材といえます。時代を超えて、庶民の夏を支える食文化として根付いてきた土用の丑の日。普段はあまり口にしない人もウナギを求め、食卓にちょっとしたごちそう感を添える日として広がっています。

私たちがスーパーなどで目にするウナギは養殖ものがほとんどで、その大半はオスです。ウナギは生まれたとき性別がなく、生育環境によって性別が決まる“性分化”する生態です。ストレスの多い養殖環境では、自然とオスに性分化する傾向があります。一方、自然の河川や汽水域で獲れる天然ウナギは、成長が早く大型化しやすいことから圧倒的にメスが多く、しかも良質な個体は老舗専門店などに優先的に卸されます。熟練の職人が仕上げる極上の蒲焼は、脂のノリと旨味が段違いで、しっとりふわっと口にとろけます。
これぞまさに、うなぎの真骨頂。

料亭の世界では昔から“ウナギはメスが旨い”と重宝されてきたともいわれるほど。
実は、養殖でもまれに成長の良いメスが混じることがあります。性別で選別されずに出荷されるため、偶然そのメスに“当たった”時は、まるで宝くじに当たったような特別感。脂の旨味やしっとりした舌触りは、やはり格別です。そして近年、大豆イソフラボンなどを含む飼料で、性分化の仕組みをコントロールし、意図的に“メス化”させた養殖ウナギが登場。代表格は三河一色産の「うなくい〜ん」。その名の通り、“うなぎ界の女王”として注目されています。ほかにも「艶鰻」「でしこ」「葵うなぎ」など、メスに特化した新ブランドが次々に誕生しています。

老舗専門店でしか味わえなかった、しっとりとした脂と奥行きのある旨味を、家庭でも手軽に楽しめる時代がやってくるかもしれません。夏の贅沢が、もう少し身近に感じられる…そんな期待もふくらみます。
ちなみに、蒲焼には関東風と関西風の違いがあります。関東風は、蒸してからタレ焼きするスタイルで、ふわトロとした上品な食感が特徴。対して関西風は、生のまま直火で焼き上げるため、皮はパリッと、身はふっくらと香ばしく仕上がります。どちらも甲乙つけがたい魅力です。
関東風の“ふわトロ”と関西風の“パリふわ”の違いこそあれ、極上のメスウナギで味わえるのならば、ウナギ好きとしてはこれほど嬉しいニュースはありません。

ウナギと、口の脂分をウォッシュ効果で洗い流してくれる「菊正宗 純米樽酒」の相性は抜群。冷やして飲めば、夏の暑さも忘れるような爽快感が口いっぱいに広がります。
この夏も、土用の丑の日にウナギを。伝統と革新が出会って生まれた新しいごちそうで、今年の夏も、そしてこれからの夏も、心も身体も元気に乗り切りたいですね。
菊正宗ネットショップはこちらから
▼https://www.kikumasamune.shop/