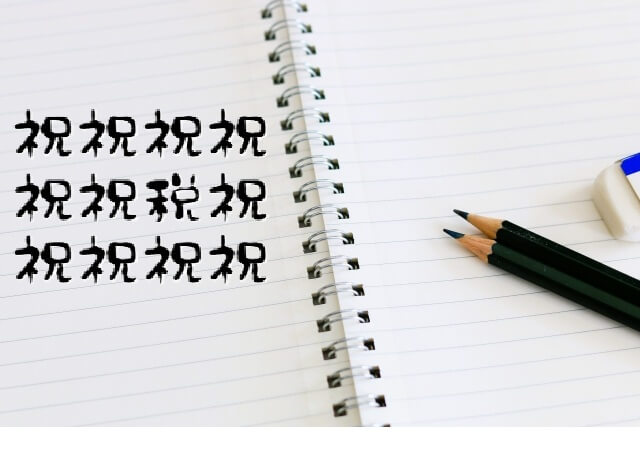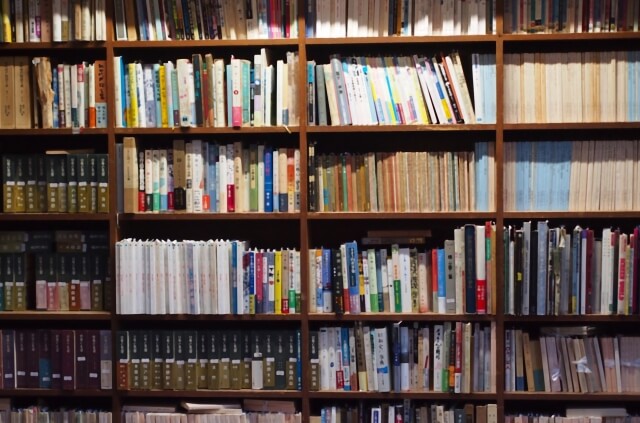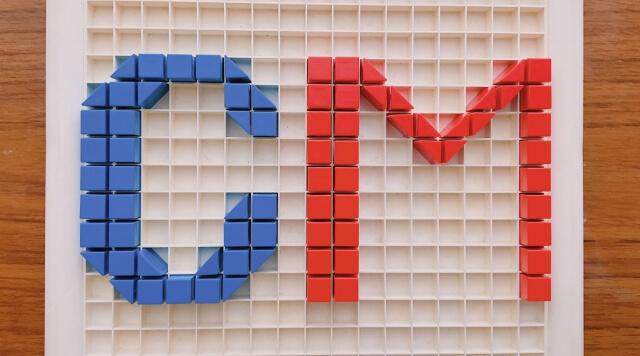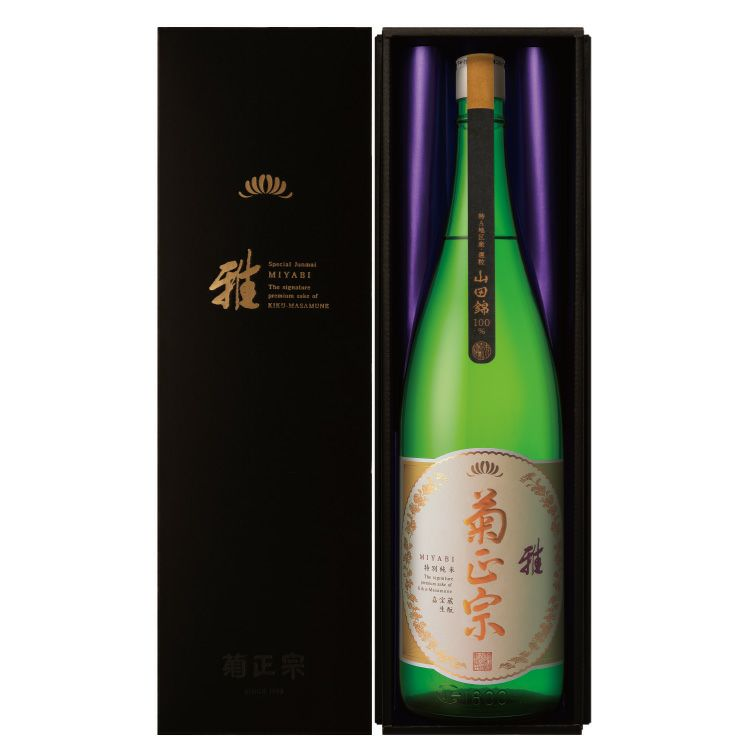江戸の縁起担ぎから現代のキャラクターへ。愛らしさが、最大の猫の魅力。
9月29日は「招き猫の日」です。その由来は“くる(9)ふく(29)=来る福”の語呂合わせからきています。商売繁盛や開運招福の象徴として広く知られる招き猫。その背景には、日本人が大切にしてきた縁起担ぎや遊び心を垣間見ることができます。
招き猫は、上げている手によって意味が異なります。左手を上げているものは、人との縁や千客万来を願う姿です。右手を上げているものは金運や商売繁盛を招き、両手を上げているものは福も人も一度に呼び込むとされます。さらに毛色にも意味があり、三毛猫は幸運、黒猫は厄除け、白猫は開運と、それぞれの思いが込められています。

猫が日本に伝わったのは奈良時代。仏教の経典をネズミから守るため、古代中国から船に同乗してやって来たといわれています。950年、宇多法皇が「寛平御記」に猫を飼っていたと記したことが、日本最古の“飼い猫”に関する記録。渡来当初は実用面で重宝されましたが、やがて宮中で可愛がられ、平安時代の和歌にも数多く詠まれました。とくに室町から江戸にかけて盛んになった養蚕業でも繭を食べるネズミ退治に欠かせない存在となり、猫は人々にとって“福をもたらす身近な生き物”として浸透していきました。

江戸時代中期、徳川綱吉の「生類憐みの令」では、猫を紐でつないで飼うことが禁じられ、町中で自由に歩き回る姿が庶民の生活に溶け込んでいきます。米や書物、繭玉や織物をネズミから守る猫は生活に直結した頼もしい存在。その自由気ままなツンデレ姿は、人々をさらに魅了しました。さらに夜目が利くことから、魔を払う不思議な力を持つと考えられ、毛色や姿に意味を重ねる習俗が広がりました。これが、招き猫のような縁起物へとつながっていきます。
猫は浮世絵や戯作にも多く描かれました。なかでも歌川国芳は無類の猫好きとして知られ、擬人化したユーモラスな猫の絵を数多く残しています。歌川広重や国貞も作中に猫をさりげなく登場させるなど、猫は江戸庶民にとって“かわいらしい福の象徴”として定着していきました。

平和な時代が続いた江戸中期以降、武士や公家中心の文化から町民文化が大きく花開きます。歌舞伎や浮世絵、年中行事や縁起物が庶民の暮らしを彩り、そのなかで“招く”という言葉は頻繁に用いられました。歌舞伎の顔見世興行では「まねき看板」に役者の名を大書して観客を呼び込み、店先の招き猫もまた福や人を呼び、商売を盛んにする願いを託されたのです。さらに「春夏冬二升五合=商い益々繁盛」と読む“判じ物”のように、江戸庶民は文字や絵に意味を重ねる遊び心を愛しました。その精神が招き猫にも宿り、ただの置物を超えて文化を象徴する存在へと育っていったのです。

現代に生きる私たちにとっても、招き猫はユーモラスで庶民的なキャラクターとして親しみやすい存在です。9月29日の「招き猫の日」に、改めてその由来と文化的背景に触れてみるのも一興。ちょっとした猫の仕草の裏に、江戸庶民の祈りや洒落心が見え隠れすることを思うと、招き猫を眺める時間が一層楽しくなるはずです。
菊正宗ネットショップはこちらから
▼https://www.kikumasamune.shop/