
身近なアノ現象は、さまざまな分野の研究により解明されています。
今回は、日常で出くわす“アノ現象”のお話です。テレビを観ていて、よく知っているタレントなのにどうしても名前が出てこない。顔やイメージは浮かぶのにどうしても思い出せない。そんなとき、“ほら、あのドラマに出て、〇〇という女優さんと共演してた”“〇〇って誰だっけ”と、会話がどんどん記憶の深い沼に沈んでいきます。これは「舌先現象(TOT現象)」や「ベイカーベイカーパラドクス(“名前”より“職業”の方が記憶に残りやすいという逆説的な現象)」と呼ばれ、俗に「アレアレ症候群」ともいわれます。名前に限らず、頭の中に答えはあるのに言葉が出てこない状態です。

こうした日常の“?”は数多く存在し、それらを総称してアノ現象と呼びます。心理や行動を分析すると“あるある”はいっぱい。たとえば試験勉強や山積みの仕事を前に、つい部屋を片付け始めるのは「セルフハンディキャッピング」。失敗しても自分の心が傷つかないように、あらかじめ言い訳理由を用意する心の働きです。何かを取りに別の部屋に行ったのに目的を忘れてしまう「ドアウェイ効果」もよく知られています。似た言葉に「ドアノブ効果」があります。これは、部屋を出る直前に思わず本音を漏らしてしまうという現象です。
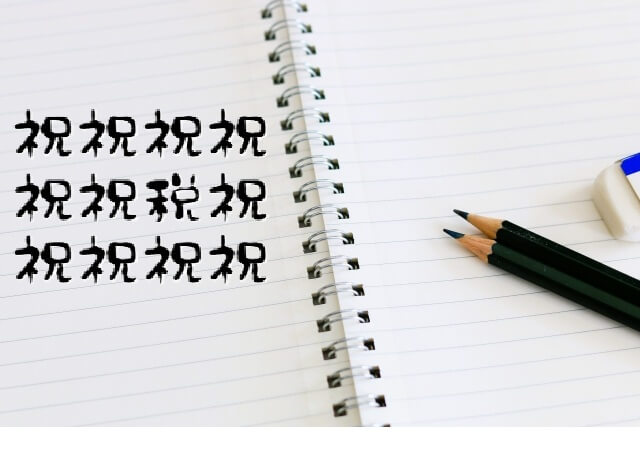
また「ゲシュタルト崩壊」は、少し前のドラマ「逃げ恥」で注目されました。同じものを見続けると脳が疲労したり、注意力が散漫になったりすることで、全体をまとめる機能が弱まるというもの。同じ漢字を何度も書いている際に、文字としての認識が薄れ、“あれっ、こんな字だった?”となるあの体験です。ユニークなのは40年前に話題になった「青木まりこ現象」。本屋に行くと急に便意をもよおすという彼女の投稿から生まれ、テレビ特番も組まれました。インクの匂いや自律神経、不安効果などの説は出ましたが、いまだに解明されていません。
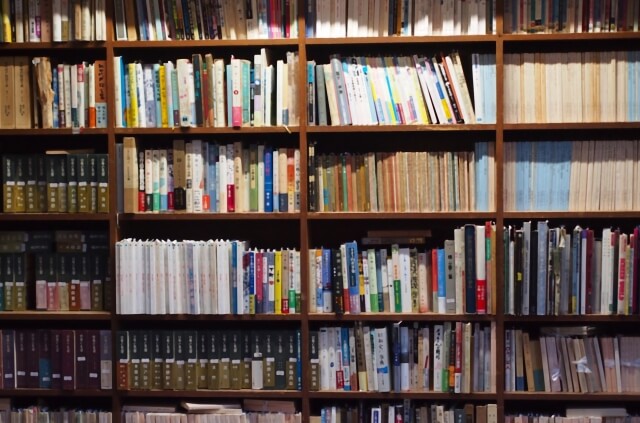
これらの現象は決して特殊な人にだけ起こるのではなく、人類共通の“あるある”として誰もが体験していることが大きな魅力です。専門用語は難しくても、身近な体験に置き換えれば「ああ、それある!」と共感できるのです。
甘味が強いほど香りが際立って感じられるのは、脳が味覚と嗅覚の情報を統合している証拠とされています。これと似た体験が辛口の日本酒でも起こります。辛口=ドライという印象がある一方で、実際に口に含むと奥深い穀物の香りや吟醸香が鮮やかに立ち上がってくるのです。

これは辛口のキレが余韻を透明にし、香りを“解放”しているからであり、辛口だからこそ香りがクリアに際立つ。そんな一瞬の味わい体験もまた、私たちの脳が生み出す“アノ現象”。菊正宗の“うまいものを見ると、菊正が欲しくなる。辛口の菊正を飲むと、うまいものが食べたくなる”というCMの言葉は、その感覚を見事に言い当てているのかもしれません。
「菊正宗 上撰 1.8L」
居酒屋でお馴染みのキクマサ!
きもと造りは、現在酒造りの主流である市販の乳酸菌を添加する手法とは異なり、生きた乳酸菌の力を借り、力強い酵母をじっくりと育てる伝統の酒造りです。
スッキリと雑味がなく、しっかりとした押し味とキレのあるのど越しが特徴の、料理の味が引き立つ本流辛口酒です。

菊正宗ネットショップはこちらから
▼https://www.kikumasamune.shop/
