お客様各位
平素は多大なるご愛顧を頂きまして誠にありがとうございます。
台風10号の接近に伴い、全国的に商品のお届けに遅れる可能性がございます。
詳細はヤマト運輸ホームページをご確認ください。
https://www.kuronekoyamato.co.jp/ytc/chien/chien_hp.html
大変ご迷惑をお掛けしますが、ご了承くださいますよう、よろしくお願いいたします。

極上辛口のお酒をお探しなら菊正宗ネットショップへ!清酒(樽酒、純米酒、大吟醸酒)はもちろん、酒粕、おつまみ、日本酒の化粧品まで豊富な品揃え!
お客様各位
平素は多大なるご愛顧を頂きまして誠にありがとうございます。
台風10号の接近に伴い、全国的に商品のお届けに遅れる可能性がございます。
詳細はヤマト運輸ホームページをご確認ください。
https://www.kuronekoyamato.co.jp/ytc/chien/chien_hp.html
大変ご迷惑をお掛けしますが、ご了承くださいますよう、よろしくお願いいたします。
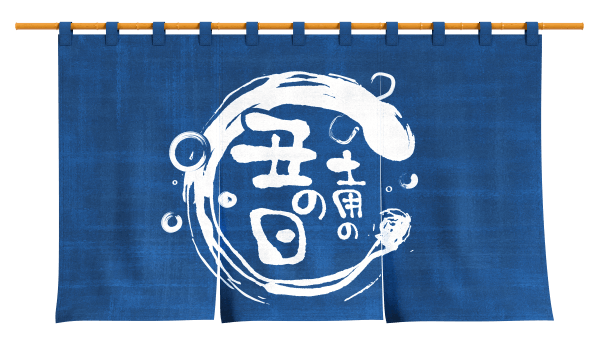
今年の夏の土用期間は、
7月19日から8月6日で、
翌日の8月7日は“立秋”です。
“立春”“立夏”“立冬”直前にも、
それぞれ18日前後の土用期間があり、
これらは移りゆく季節の節目に
位置づけられます。
今年の夏の「土用の丑の日」は2回で、
7月24日を“一の丑”、
8月5日を“二の丑”と呼びます。
「土用の丑の日」に
ウナギを食べる習慣を広めたのは、
江戸時代の蘭学者・平賀源内。

夏場にウナギの売り上げが落ちる
と相談された平賀源内が、
店先に
“本日丑の日 土用の丑の日 うなぎの日
食すれば夏負けすることなし”
という看板を立てるよう
助言したことが発端です。
それが見事に成功し、
お店は大繁盛。
ほかのウナギ屋も
それを真似るようになりました。
その結果、
次第に江戸の庶民の間で
夏の「土用の丑の日」に
ウナギを食べる習慣が根付いた
というのが通説です。
これが
日本で最初の広告キャッチコピー
ともいわれています。
実際、ウナギには
ビタミンAやビタミンB群、
ビタミンDなど、
疲労回復や食欲増進に効果的な成分が
多く含まれ、
夏バテ防止にはピッタリの食材。
昨今の連日の酷暑も、
ウナギの栄養価で
なんとか乗り切れそうな気さえするから
不思議です。

さて、ここからが本題です。
ひと月も前に終わった
夏の「土用の丑の日」を
取り上げるには理由があります。
各季節の土用期間を決める基準は、
その直後に訪れる二十四節気の
立春、立夏、立秋、立冬です。
二十四節気は
太陽の動きを基に定められており、
旧暦(太陰太陽暦)、
新暦(太陽暦)のどちらにも
同じ日が適用されます。
しかし、
旧暦の明治5年12月2日の翌日が
新暦の明治6年1月1日になったため、
新暦では約1カ月季節が早くなり、
それまでの季節と歳時記に
ズレが生じるようになりました。

これが
「暦の上では…」
とよくいわれる理由です。
そのズレを現在に当てはめると、
“一の丑”の7月24日は8月27日、
“二の丑”8月5日は9月7日にあたり、
現在の残暑の時期と
重なることになります。
さて、
市場に出回っているウナギの
約99%以上は養殖もので、
天然ウナギは、わずか1%未満
というデータがあります。
本来、脂がのって美味しい旬は
秋から冬にかけての10〜12月頃です。
しかし、
夏の「土用の丑の日」に出荷される
養殖ウナギは、
一般的に6~8月頃が旬とされています。

これは養殖ならではの特徴ともいえ、
夏の繁忙期に合わせて
出荷調整が行われているためです。
なので、
春や冬に出荷される養殖ウナギも
市場に流通する時点が旬なので
季節による味の違いはありません。
日本人のウナギ好きは
江戸の昔から続く
伝統的な食文化のひとつです。

とくに東京には
歴史を重ねた老舗が多く、
昭和の文豪たちも
ご贔屓の店を
その作品に登場させています。
福沢諭吉や谷崎潤一郎、太宰治、
夏目漱石、斎藤茂吉、泉鏡花…
そして食通で名高い池波正太郎も
その一人です。
最近では、
日本を訪れる外国人の間で
“うな重”や“ひつまぶし”も
人気を博しています。
この先もウナギの文化、
続いてほしいものです。
鰻の旨みを高める
「菊正宗 純米樽酒 720mL」

▼菊正宗ネットショップはこちらから
https://www.kikumasamune.shop/

夏は暑さや湿気によって
大量に汗をかきます。
体内の水分とともに
栄養素も外に排出され、
これが夏バテの原因となります。
酷い時には
脱水症状や
熱中症を引き起こすこともあるため、
こまめな水分補給が必要です。

また、夏バテ気味で
食欲不振になりがちなこの季節には、
あっさりとして食べやすい
夏野菜が栄養補給に適しています。
昨今、普段使いの野菜は
ハウス栽培などによって
一年を通して出回っているため、
利便性が高い反面、
旬が分かりにくくなっています。
しかし、旬の時期に採れる野菜は、
生育に適した自然環境で育ち、
もっとも栄養価が高い時期に
収穫されます。
つまり、
その野菜のピークともいえる栄養を
ふんだんに摂取できるだけでなく、
その時期に
人の身体が欲している栄養素を
豊富に含んでいるのが魅力です。

旬の夏野菜に含まれる
水分やカリウムは、
汗で不足しがちな水分を補給し、
熱のこもった身体を
内側からクールダウンさせます。
また、
さまざまなビタミンが
身体の調子を整えてくれるのです。
野菜の味そのものも濃いため、
野菜本来の美味しさを
感じられるのが特徴です。

同様に、春野菜は
ビタミン、
ミネラル、
食物繊維が豊富で、
疲労回復に効果的。
秋野菜には
免疫力の向上が期待できる
βグルカンやビタミンC
といった栄養素が多く含まれ、
風邪の予防などに効果的です。
冬野菜は
ビタミンやβ-カロテン
などの栄養素が豊富で、
血行促進によって身体を温めたり、
免疫力を高めて
風邪などを予防する効果が
期待できます。
旬の野菜は、美味しいだけではなく、
季節に応じた健康づくりにも
効果絶大なのです。
さて、夏野菜といえば、
ビタミンCとE、
β-カロテン、リコピンなど、
抗酸化作用を担う栄養素の宝庫
“トマト”が代表格です。
体内に溜まった活性酸素を除去し、
免疫力を高めてくれます。
また、水分を多く含む“キュウリ”は
水分補給に効果的です。
汗とともに失われがちな
カリウムを多く含み、
酢と一緒に取るとビタミン C が
効率良く摂れます。
外皮に
ポリフェノールを多く含む“ナス”は
抗酸化作用、血圧調整に最適。
食物繊維も多く、
整腸作用が期待できます。

ピーマンやゴーヤ、オクラなど
夏バテ解消に適した野菜も
食べておきたいものです。
日本の料理は多様で、
和洋中の大きな分類だけでなく、
インド料理、
イタリア料理、
韓国料理など、
さまざまな料理が楽しめるのが
魅力です。
家庭料理でも、
毎日のように
異なる献立を楽しむことができます。

たとえば、夏野菜の“トマト”。
生のままスライスして
副菜として
食卓に並ぶことも多いですが、
主菜として
調理されることも少なくありません。

“トマトとオクラの和風マリネ”や
“トマト素麺”
“トマトとキュウリの中華風ツナサラダ”
“トマトとマグロの冷製カッペリーニ”
“トマトとモッツアレラのカプレーゼ”
“牛肉とトマトのキムチチーズ焼き”
“夏野菜のキーマカレー”
“夏野菜のラタトゥイユ”など、
バラエティ豊かなレシピがあります。
調理方法を変えて、
飽きることのない
美味しさを持続しながら
夏の暑さを乗り切りましょう。
菊正宗ネットショップはこちらから
https://www.kikumasamune.shop/


「西馬音内の盆踊(秋田)」、
「郡上おどり(岐阜)」と並んで
“日本三大盆踊り”
のひとつに数えられるのが
「徳島市阿波おどり(徳島)」です。
また、
「よさこい祭り(高知)」、
「新居浜太鼓祭り(愛媛)」と一緒に
“四国三大祭り”のひとつとしても
知られています。

徳島の「阿波踊り」の歴史は
約400年にわたり、
その起源には3つの説があります。
まずは
鎌倉時代の念仏踊りから続く
先祖供養のための踊りを起源とする
“盆踊り起源説”、
次に
戦国時代末期に勝瑞城で
行われていた風流踊りを起源とする
“風流踊り起源説”、
そして1586年(天正14年)に
徳島藩藩祖・蜂須賀家政が
無礼講として踊りを許したとされる
“築城起源説”です。
一般的には盆踊りを元に、
組踊りや俄(にわか)などと融合して
徳島の伝統芸能として定着したものが
「阿波踊り」と考えられています。

江戸時代には踊りの熱狂ぶりが
一揆につながる恐れがあるとして
徳島藩から幾度も禁止令が出され、
明治時代にも文明開化と
相容れないとして3年にわたり
取締令が出されました。
2017年(平成29年)には
大きな累積赤字が発覚するなど、
何度かの廃止にも近い危機を
乗り越えて現在に至っています。
今年の「徳島市阿波おどり」は、
8月11日から15日に開催されます。
人口約25万人の徳島市市街地に
設けられた桟敷席を中心に、
国内外から100万人を超える観光客が
集まることが予測されています。
普段の約5倍の人口密度になるため、
静かな町は一気にお祭りムード一色に
彩られることになります。
本家徳島に勝るとも劣らない
賑わいを見せるのが、
「東京高円寺阿波おどり(東京)」。
約1万人の踊り手が集結し、
観光客も約100万人が詰めかける
恒例となった東京の夏の風物詩です。
約60万人が来場する
「南越谷阿波踊り(埼玉)」とともに
“日本三大阿波踊り”
と呼ばれています。
「阿波踊り」は三味線や太鼓などの
2拍子の伴奏にのって、
“連(れん)”と呼ばれる
踊り手の集団が練り歩きます。

“連”にはそれぞれ流派があり、
その特徴が顕著に現れるのが
“男踊り”です。
背筋を立てて腰をぶらすことなく
上半身を自由に明るく踊るのが
“のんき連”で、
もっとも歴史が古いグループです。
最高峰と呼び声の高い
“娯茶平(ごちゃへい)連”は、
腰を低く落とし前傾姿勢で
スローなテンポで地を這うような
タメの利いた渋い踊りが特徴です。
手持ち提灯を片手に、
前傾姿勢でリズミカルに
激しい暴れ踊りを披露するのは
“阿呆連”。

これら3つの連を
三大主流と称していますが、
これ以外にも特徴的な“連”が
数多く競うように踊るのが
「阿波踊り」の最大の見せ場です。
女性が“男踊り”を披露する
“連”も多く、しなやかな切れが
魅力といわれています。
一方、“女踊り”は、
じゅばん、裾除け、手甲、
下駄の出で立ちで、
編笠を深く被って
一糸乱れぬ踊りを披露します。
その姿は艶やかで
上品な所作が特徴です。
実際に現場で
その臨場感に包まれるのが、
「阿波踊り」の醍醐味といえます。
その感覚は、野外ロックフェスで
多くのバンドが登場して
観客を魅了するのに
似ているかも知れません。

旅のお供にピックアップ!お酒とおつまみセットです。
菊正宗ネットショップはこちらから