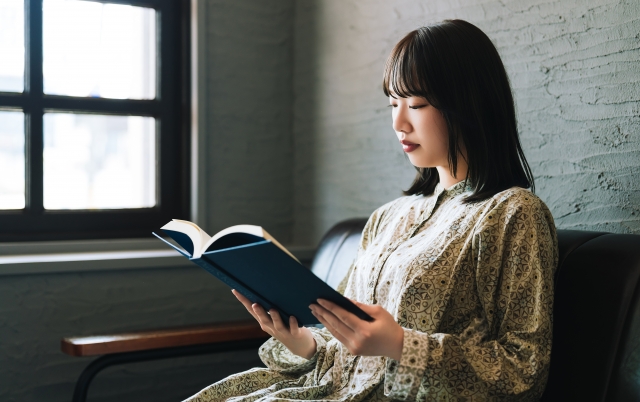
スマホ時代だからこそ、あえて“紙で読む文化”にこだわりたい。
厳しい暑さも少し和らぎ、朝夕の涼しい風に感じる秋の気配。秋の旬の味覚を楽しむ“食欲の秋”や涼しくなって運動がしやすくなる“スポーツの秋”など、さまざまな“〇〇の秋”を楽しむ季節になりました。とりわけ、秋の夜長を楽しむ意味を持つ「読書の秋」は、落ち着いた季節に心ゆくまで物語の世界に浸る贅沢が不思議と似合います。1947年(昭和22年)、戦争で荒廃した社会に、精神的な豊かさを取り戻したいという強い願いで読書週間がスタート。

終戦直後の物資も食料も乏しかった時代でしたが、文化や心の復興への願いが「読書の秋」の言葉とともに定着しました。それを支えたのは、町のあちらこちらにあった貸本屋です。物資が少なく娯楽もほとんどない時代、古本を再利用するという発想が「読書の秋」の原動力となりました。1960年代後半頃まで日常に溶け込んでいた貸本時代、人々を魅了したジャンルに怪奇・探偵・冒険小説があります。怪人二十面相や少年探偵団の江戸川乱歩や金田一耕助シリーズの横溝正史などが人気で、安く借りられる貸本は庶民の強い味方でした。また、好きなジャンルの作品を読み漁り、その影響を受けた楳図かずおや水木しげる、松本零士などの後の漫画界の巨匠たち。

彼らもデビュー間もないころは貸本で作品を発表して人気を不動のものに。そのダントツの人気を誇ったのが他ならぬ手塚治虫作品でした。
このほか、夏目漱石、太宰治、志賀直哉などの純文学系作家や子母澤寛、山本周五郎、柴田錬三郎などの時代小説、石坂洋次郎、獅子文六、有吉佐和子などの通俗・恋愛青春小説など多彩なジャンルが本屋の棚に並んでいました。シャーロック・ホームズや名探偵ポワロなどの推理小説をはじめ、海底二万里や宝島などの冒険小説など翻訳された海外作品が広まったのも貸本屋が起点です。1959年に創刊が相次いだ少年週刊漫画雑誌も発刊当初は貸本文化の延長線上にありました。

漫画雑誌には汚れ防止の透明ビニールやセロファンが掛けられ、貸出しの順番を待つ子どもたちの姿も日常の光景でした。いつも最初に借りる子は人気者で、その子の家で回し読みすることが放課後の楽しみのひとつだったのです。
やがて、高度経済成長期を迎えて世帯収入が増え、小説も文庫本として、より安価に購入できるようになり、貸本屋は町の一般書店へと業態を変化。小説や漫画を原作とした映画やテレビドラマも増えたことで、庶民の娯楽は一気に広がりました。かつて多くの人々を魅了した小説も、時代の流れの中で活字離れという局面に接して、本が売れない時代へと突き進むことに。
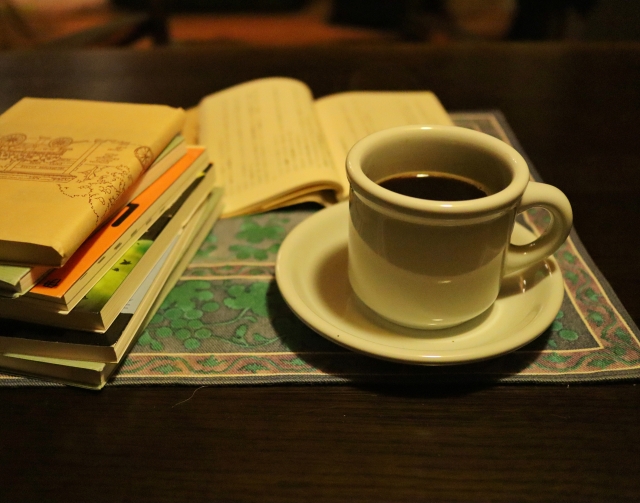
あれから半世紀を経た現代、本を取り巻く環境は大きく様変わりしています。多くの漫画はアニメ化され、原作の漫画書籍とともに世界中にファンを持つ最強コンテンツへと成長。また漫画や小説から生まれたドラマや映画も花盛りです。漫画や小説もスマホで読む時代へと移り変わる中、インクの匂いと一緒にあのワクワクした昔の思い出が蘇ります。ドラマや映画きっかけでも構わないので、単行本や小説で登場人物とじっくり向き合う“読む文化”を、この季節に楽しんでみてはいかがでしょうか。本のページをめくるたびに、あの頃の静かな時間がそっと戻ってくるかもしれません。
ほろよい 720mL
アルコール度数8%でほろよいの気分を楽しめます。
口に含んだ瞬間にふわっと広がるフルーティな香りと、ブドウのような優しい甘み、プラムのような酸味が特長のお酒です。

菊正宗ネットショップはこちらから
▼https://www.kikumasamune.shop/
